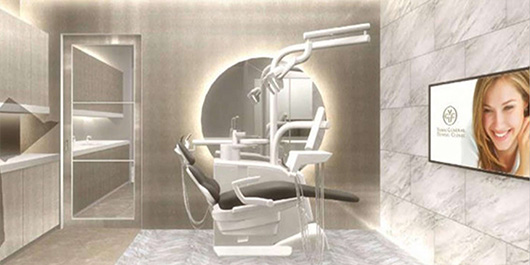人と会話をしているとなんだか聞き取りにくいと言われたり、自分でもうまく発音できなかったりすることはありませんか?
実はその原因は、歯並びにあるかもしれません。
滑舌の良し悪しは、舌や唇の使い方だけでなく、歯や顎の位置関係にも深く関係しています。
この記事では、滑舌に影響する歯並びの特徴や、なぜ発音がしづらくなるのか、改善方法について詳しく解説します。
目次
■滑舌が悪いのはなぜ起こるのか
◎発音は口の形に左右される
私たちが話す時、舌、唇、歯、軟口蓋など、口の中のさまざまな部位が連携して音を作り出しています。
これらの動きがスムーズでなければ、空気の流れや舌の接触に乱れが生じ、発音に違和感が出てしまいます。
特に「サ行」や「タ行」「ラ行」といった音は、舌と歯の接触が重要なため、歯並びが乱れていると舌の位置が安定せず、発音が不明瞭になってしまいます。
■滑舌に影響を与える歯並びの特徴とは
◎出っ歯(上顎前突)
前歯が前方に突き出ている状態では、空気がうまくコントロールできず、発音がぼやけたり、「ス」「ズ」などの音で息が漏れやすくなったりします。
また、舌が前方に出やすくなるため、舌足らずな話し方になることもあります。
◎受け口(下顎前突・反対咬合)
下の前歯が上の前歯よりも前に出ていると、舌の動きが制限され、発音に支障が出やすくなります。
特に「ラ行」「ナ行」「ダ行」などの舌先を使う音で、言葉がこもって聞こえるようになります。
また、日本語以外の外国語を発音する際にも、支障が出ることがあります。
◎開咬
奥歯を噛み合わせた際に上下の前歯が噛み合わず、隙間が空いている状態では、息が前方に抜けてしまい、音が漏れるようになります。
「ツ」「チ」などの破擦音や、英語の「th」などを発音する際に特に影響が大きいです。
開咬の多くは、幼少期の指しゃぶりや舌癖によって起こるため、生活習慣の見直しも必要です。
◎すきっ歯(空隙歯列)
中心の前歯2本の間に隙間がある状態も、空気の通り道が変化するため滑舌に影響する場合があります。
「シ」「ス」「セ」「ソ」といった音が漏れやすく、「シュッシュッ」と空気が抜けるような音になることも。
見た目の問題だけでなく、発音にもデメリットがあるため、気にされる方も少なくありません。
■歯並びによる滑舌の問題は矯正で改善できる?
◎歯列矯正で発音が安定することがある
歯並びを整えることで、舌のポジションが安定し、音を発する際の支障が少なくなります。
特に開咬や出っ歯、受け口といった発音に影響しやすい不正咬合は、矯正治療によって改善の可能性があります。
成人矯正でも、発音の改善を目的とする方は少なくありません。
マウスピース矯正などは、発音時の影響が少ないため、仕事や日常生活にも支障なく治療が進められる点がメリットです。
◎口腔筋機能療法(MFT)で舌の使い方を訓練
滑舌の改善には、歯並びだけでなく「舌の使い方」を変えることも大切です。
MFT(口腔筋機能療法)では、舌、唇、頬などの筋肉の動かし方をトレーニングし、正しい発音や咀嚼の仕方を学んでいきます。
矯正治療とMFTを併用することで、歯並びだけでなく、根本的な滑舌改善につながるケースも多く見られます。
◎早めの対処が滑舌と見た目の両方にメリット
滑舌の問題が歯並びに関係している場合、早期に治療することで、発音のクセが固定される前に改善しやすくなります。
また、見た目のコンプレックスも良くなり、自信をもって会話できるようになる方も多いです。
【滑舌に悩んでいるなら歯並びを見直してみよう】
滑舌の悪さは、単なる話し方の癖や個性と片づけられがちですが、実は歯並びに起因しているケースが少なくありません。
出っ歯や開咬、受け口など、発音に関わる歯並びの乱れは、矯正によって治る可能性があります。
さらに、口腔筋のトレーニングを併用すれば、滑舌の悩みが根本から解消される可能性も高くなります。
滑舌が気になっている方は、お気軽にご相談ください。